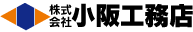高槻で使えるリフォームの減税・支援制度
リフォームの減税・支援制度
税制・減税
●住宅ローン減税〈2025年12月31日入居分まで〉
住宅ローンの年末残高により所得税を控除することができる

●主な要件
- (1)自らが居住するための住宅
- (2)床面積が50㎡以上
- (3)合計所得金額が2,000万円以下
- (4)住宅ローンの借入期間が10年以上
- (5)引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居
- (6)昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合
●詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。
三世代同居改修促進税制
三世代で同居するためにキッチン・バス・トイレ・玄関のいずれかを増設した際、所得税(ローン型/投資型)が減税される
概要・・・
要件・・・
- ①三世代が同居する住宅※であること
- ②三世代同居改修工事
(次のイ~ニの1種類以上を増設し、工事後にイ~ニの2種類以上が複数になる工事)であることイ:キッチン(シンク、コンロ又はIH、換気設備があること)
ロ:浴室(浴槽又はシャワーがあること)
ハ:トイレ(大便器があること)
ニ:玄関(玄関扉と土間があること)[対象工事例]
・改修前にトイレが複数ある住宅でキッチンを増設
・改修前にイ~ニが1つずつの住宅でトイレ、バスを増設 - ③三世代同居改修工事に要した費用の合計が50万円超
- ④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
固定資産税の減額
概要…
について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)について1/3を減額。
要件…
イ:65歳以上の居住者 ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者 ハ:障害者②一定のバリアフリー改修工事を実施すること。
イ:廊下の拡張 ロ:階段の勾配の緩和 ハ:浴室改良 ニ:便所改良
ホ:手すりの設置 ヘ:段差の解消 ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
③バリアフリー改修工事に要した費用の合計が50万円超。(但し補助金等をもって充てる部分を除く)
④バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して、市区町村に申告すること。
⑤床面積が280㎡以下の住宅であること
期限…
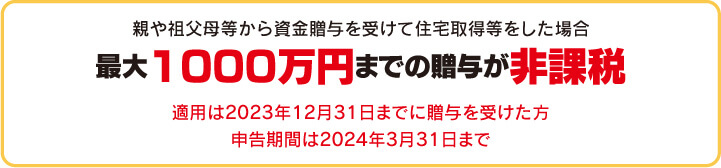
バリアフリー改修促進税制
●バリアフリーリフォームを行った際、所得税(ローン型/投資型)、固定資産税が減税される!
概要…
要件…
イ:50歳以上の居住者 ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者 ハ:障害者
ニ:居住者の親族のうち、上記ロ若しくはハに該当する者、又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
②一定のバリアフリー改修工事を実施すること。
イ:通路等の拡幅 ロ:階段の勾配の緩和 ハ:浴室改良 ニ:便所改良
ホ:手すりの設置 ヘ:段差の解消 ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
③50万円を超える工事。(但し補助金等をもって充てる部分を除く)
④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して、確定申告すること。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可
期限…
固定資産税の減額
概要…
について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)について1/3を減額。
要件…
イ:65歳以上の居住者 ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者 ハ:障害者②一定のバリアフリー改修工事を実施すること。
イ:廊下の拡張 ロ:階段の勾配の緩和 ハ:浴室改良 ニ:便所改良
ホ:手すりの設置 ヘ:段差の解消 ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
③バリアフリー改修工事に要した費用の合計が50万円超。(但し補助金等をもって充てる部分を除く)
④バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して、市区町村に申告すること。
⑤床面積が280㎡以下の住宅であること
期限…
長期優良住宅化リフォーム減税
●省エネリフォーム等と併せて耐久性向上リフォームを行った際、所得税(投資型/ローン型)、固定資産税が減税される!
概要…
要件…
イ:小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
ロ:給排水管、給湯管に関する維持管理、若しくは更新を容易にするための工事
②改修部位の劣化対策、維持管理・更新の容易性がいずれも、増改築の長期優良住宅の認定
基準に基づくものであること。
③省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超。
④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して、確定申告すること。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外 ※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
期限…
固定資産税の減額
概要…
要件…
イ:小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
ロ:給排水管、給湯管に関する維持管理、若しくは更新を容易にするための工事
②改修部位の劣化対策、維持管理・更新の容易性がいずれも、増改築の長期優良住宅の認定基準に基づくものであること。
③省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超。
④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して、確定申告すること。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外 ※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
期限…
耐震や省エネリフォームとあわせて行う耐久性向上のリフォームは、税の控除が受けられます
ローン型減税
5年以上の住宅ローンを借りて、一定の省エネリフォームとあわせて一定の耐久性向上リフォームをした場合に利用できる制度です。リフォームローンなどの年末残高のうち、対象となるリフォーム費用の2%および他のリフォーム費用の1%が、リフォーム後、居住開始した年から5年間、所得税から控除されます。
投資型減税
住宅ローンの借り入れがなくても使える制度です。耐震リフォームまたは、省エネリフォームとあわせて一定の耐久性向上リフォームをし、長期優良住宅(増築・改築)の認定を受けた場合、控除対象限度額を上限として、工事費等の10%が1年間、所得税から控除されます。太陽光発電設備を設置する場合や、耐震や省エネ、バリアフリー、同居対応リフォームをあわせて行う場合には、限度額が増額されます。
固定資産税の減額
耐震リフォームまたは、省エネリフォームを行った住宅が長期優良住宅(増築・改築)の認定を受けた場合、リフォーム完了年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税額(120m2相当分まで)が1年間、3分の2減額されます。リフォーム工事費用が50万円以上であることなどが要件です。
減税制度の併用
ローン型減税は、投資型減税(耐震)、ローン型減税(バリアフリー・同居対応)と併せて控除が受けられます。
投資型減税は、他の投資型減税(バリアフリー・同居対応)と併せて控除が受けられます。
長期優良住宅化リフォーム減税による所得税の控除は、固定資産税の減額と併用できます。